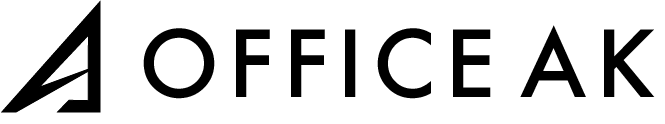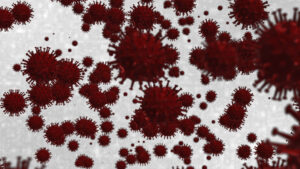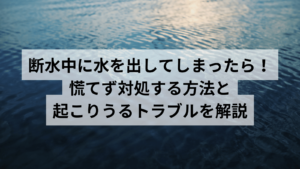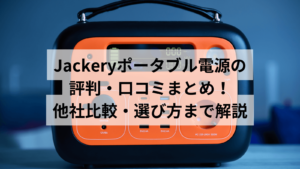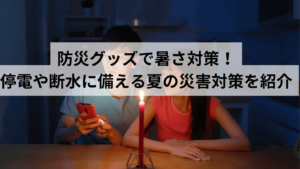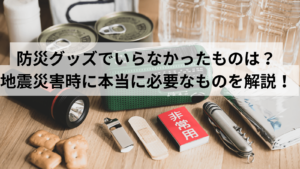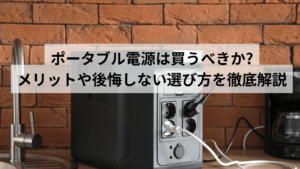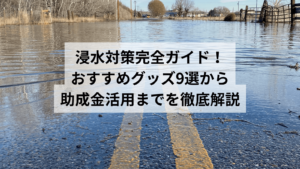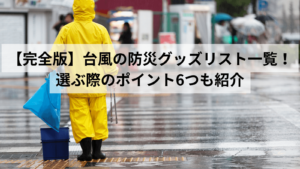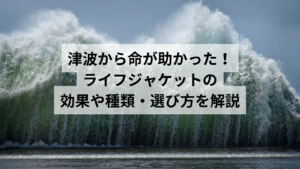本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
風水害の対策は?家庭でできる取り組みや避難するときのポイントを解説

台風や大雨が原因で起きる風水害。日本の多くの地域で発生する可能性があります。海岸の近くや山間部だけでなく都心部も油断はできません。
しかし「実際にどのような対策が必要でいざ起きたときにどうしたらいいのか」と疑問に感じないでしょうか。
そこで本記事では、風水害の対策を自宅を建てるとき、家の周囲で行える、家庭内でできるという項目別に、風水害対策を解説していきたいと思います。
避難が必要なときに知っておきたいポイントについてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読めば、今からできる対策を学べるようになり、風水害に対する不安な気持ちが軽減されるでしょう。
風水害とは?
まず、風水害とは雨や風によって発生する災害の総称です。主に以下の3つに分類されます。
・河川の氾濫
・土砂災害
・高潮による氾濫
順番に解説していきます。
河川の氾濫
河川の氾濫とは、大雨で川の水位が上がって、堤防を超えて水があふれる現象です。同じ川であっても水位のあがり方が異なります。流域面積が小さければ水位は上がりやすくなりますし、大きければ時間はかかります。
また、都市部では下水道の排水能力を超える急激な豪雨等が起きると、浸水する可能性もあります。
土砂災害
土砂崩れは、地震や豪雨などによって山の斜面の一部が急に崩れ落ちる現象です。山崩れや崖崩れと呼ばれる場合もあります。
大量の雨が降ると、斜面の土砂の間に水がたまり、土砂粒子同士の摩擦が小さくなり崩れやすくなります。地震や地下水が原因となって発生する場合も多いです。
以下の記事では、土砂災害がどのような災害かについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
>> 土砂崩れとは?起きやすい場所や原因、対策・備えるものを解説
高潮による氾濫
高潮とは、台風など強い低気圧が原因で海面の高さがいつもよりも高くなる現象です。台風が近づくと、強い風や大気圧の低下によって海面が上昇し、海水が流れ込むようになります。
高潮は強風を伴うため、風が弱いうちに避難をする必要があります。強風になってしまうと転倒する可能性が高くなってしまい危険です。
【自宅を建てるのとき】風水害対策の取り組み
ここからは実際に、風水害に対してどのような対策をしたらいいかについてまとめていきます。
まず、自宅を建てるときは以下の点に注意しましょう。
・ハザードマップで確認する
・エアコンの室外機や給湯器を高い位置に設置する
・敷地のかさ上げする
・家の基盤を高くする
・防水性の塀で囲む
・防止性の外壁を取り付ける
詳細は以下の通りです。
ハザードマップで確認する
ハザードマップとは、地震や風水害などが原因で起きる河川の氾濫や液状化、建物倒壊を最小限にするためにつくられたものです。国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」には、地域によってどんな災害が起きやすいかが記載されています。
ハザードマップを確認すると、避けるべき自宅の場所が見えてきます。特に持ち家をこれから建てる場合、事前にチェックしましょう。
○ハザードマップポータルサイト
家を建てるときには欠かせないチェックポイントです。なぜなら、いくら風水害にバッチリ備えた住宅であっても、自然の力に対抗するには限度があるからです。そもそも、災害リスクの高いところに住まないのがはるかに重要です。
エアコンの室外機や給湯器を高い位置に設置する
エアコンの室外機や給湯器は高い位置に設置するのがおすすめです。風水害で浸水が起きても利用できる可能性があるというのが理由です。コンセントの位置も高い所にある方が望ましいでしょう。
敷地のかさ上げする
盛り土などを使って敷地全体を高くして対策を行います。東日本大震災で被害にあった地域では、その後多くの住宅で敷地のかさ上げが行われていました。1F基礎部分をより高くすると安心できます。
ただ、高くするには限界がありますし、高くした分地面への重量負担が大きくなります。そのため、地盤沈下になりやすくなるため、地盤調査をして問題がないか確認しましょう。
家の基盤を高くする
自宅を建てるときに、住居部分をそもそも高い設計にする方法です。家の基礎部分を高くしたり、1Fをガレージにしたりすれば、いざというときに安心できます。
防水性の塀で囲む
既存の住宅でもできる方法ですが、家の周りを防水性の塀で囲む方法です。土のうや止水板などを利用するとさらに防水性を高められます。
ブロック塀を取り壊したり、新規でつくったりするのに助成金を出す自治体もあるため、お住まいの市区町村のホームページを見てみましょう。
防止性の外壁を取り付ける
建物の外壁に耐水性のある塗料を塗ることで、対策ができます。定期的に塗布する必要がありますが、既存住宅にも使える便利な方法です。
【家の周囲で行う】風水害対策の取り組み
次に家の周囲で行える対策です。
・屋根のひび割れ確認や修理
・雨どいの掃除や修理
・外壁
・窓ガラス
・ベランダ
・排水路の掃除
・土のうを設置
ひとつずつ順番に確認していきましょう。
屋根のひび割れ確認や修理
瓦やトタンにひび割れや剝がれがないか確認した上で、必要に応じて修理します。
雨どいの掃除や修理
雨どいに落ち葉や土砂が詰まっていると、雨漏りやシロアリの原因になるため掃除が必要です。ホウキとトングなどを用意してゴミをかき出してください。
雨どいのつなぎ目が外れていたり、故障してたりしたら直しましょう。
外壁
モルタル壁であれば亀裂やひび割れがないか、板壁であれば腐れやかびがないか要確認です。プロパンガスの家庭は、壁にしっかりと固定されているか見ておきましょう。
窓ガラス
ひび割れやガタつきは補強や修理が必要です。雨戸があると風水害のときに役に立つので、未設置の場合、後付けを検討するのがおすすめです。本体代と取り付け費用で20万円くらいから取り付けできます。
ベランダ
植木鉢や物干し竿は強風で飛ばされる可能性があります。事前に固定しておくか、すぐに家に取り込めるように整理整頓はしておくのはおすすめです。もしくは、植木鉢はベランダでなく室内に置くのもいいのではないでしょうか。
排水路の掃除
自宅周辺の排水路にゴミが詰まっていると、水が流れない原因になります。日々掃除をして万が一の時に水が流れやすいようにしておく必要があります。
土のうを設置
風水害による冠水や浸水を防ぐために、市区町村などで土のうをもらえる場合があります。冠水や浸水しやすい場所に土のうを設置すると、いざと言うときに安心です。お住まいの市区町村に確認してみてください。
【家の中でできる】風水害対策の取り組み
最後は家の中でできる風水害対策と取り組みです。具体的には以下の4点です。
・災害用で準備するもの
・避難場所や避難コースを確認
・マイ・タイムラインを作成
・雨や風の強さをイメージ
それぞれ見ていきましょう。
災害用で準備するもの
風水害に備えて以下を準備しておくのがおすすめです。避難するときに最初に持ち出す「一次持ち出し品」と災害が復旧するまでに数日間生活するために必要な「二次持ち出し品」に分けて解説します。
〇一次持ち出し品
一次持ち出し品については、用意しすぎないのがポイントです。重すぎると避難がしにくくなるため、軽量でコンパクトにまとめる必要があります。
〇二次持ち出し品
一方二次持ち出し品は、3日から5日分は準備しておくのが望ましいです。
いざ災害が発生したときは、すぐに避難しなければなりません。そのため、事前に上記の用意をしておきましょう。年に数回でもいいので、防災の日と決めて中身を点検・準備するのがおすすめです。
非常袋は1人ひとつ用意して、何か所かに分けておくとリスク分散できます。
避難場所や避難コースを確認
いざ風水害が起きて避難が必要になったときに、避難場所や避難コースが明確になっていないと慌ててしまうのではないでしょうか。
家族全員で避難ができるとも限らないため、前もって避難場所や避難経路を確認しあうことが大切です。家族一人ひとりが自力で避難場所までたどり着けるように認識を合わせておきましょう。
マイ・タイムラインを作成
マイ・タイムラインとは、災害が起きたときに一人ひとりが取るべき行動をまとめたものです。風水害が発生する可能性があるときに、避難のタイミングや場所、経路を決めておきます。
国土交通省関東地方整備局の公式HPから、マイ・タイムラインをダウンロードできます。
https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000043.html
お休みの日に家族で一度作成してみてはいかがでしょうか。
雨や風の強さをイメージ
風水害で避難が必要になったときに、実際にどれくらいの雨量や風量なのでしょうか。こういったところまでイメージできておくと、避難がしやすくなります。
雨と風の強さをまとめたのが、以下の表です。
※気象庁HP(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html)を参照に著者が作成
※気象庁HP(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kazehyo.html)を参照に著者が作成
予報用語や1時間雨量、平均風速を元に、雨や風のイメージをしておきましょう。1時間雨量が50mm以上のときは風水害が発生する可能性が高いため、気を付けてください。
避難するときのポイント
風水害の対策がバッチリできたあとは、避難するタイミングを押さえておきましょう。次のようなときは迷わずに避難する必要があります。
・市区町村や警察、消防から避難勧告や避難指示があったとき
・家屋に倒壊のリスクがあるとき
避難勧告や避難指示があれば、速やかに避難場所に移動してください。危険区域に住んでいる場合は、さらに急いで避難することをおすすめします。
また、家がきしむ、変な音が聞こえる、ドアや窓が開きにくいときは家屋が倒壊するリスクがあります。
まとめ
風水害対策は、実を言うとどこに住むかから始まっています。持ち家にしろ賃貸にしろ、まずはハザードマップにて、お住まいの地盤の安全性を確認しましょう。
○ハザードマップポータルサイト
その上で、各自対策できることを最大限行うことがとても大切です。台風の多い季節に間に合うようにまずは、準備やシミュレーションを実施してみてはいかがでしょうか。思わぬ問題が見つかり対策ができるようになるかもしれません。