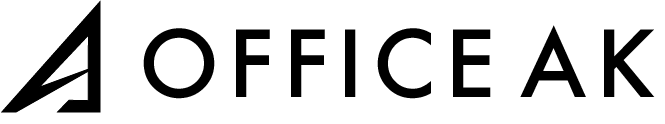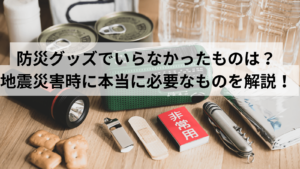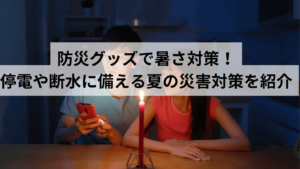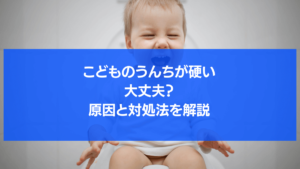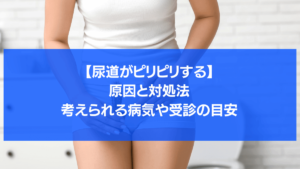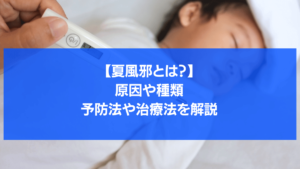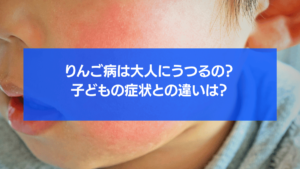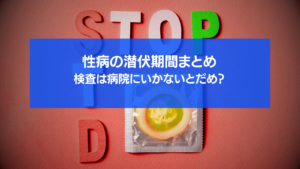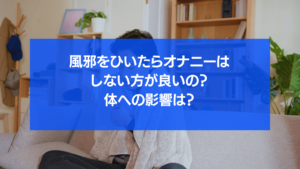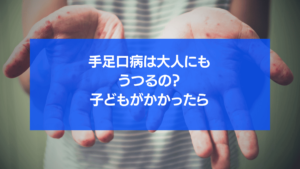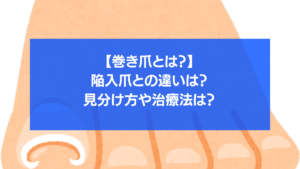本記事にはプロモーションが含まれている場合があります
【春に多い食中毒の原因と対策】家庭でできる予防法は?
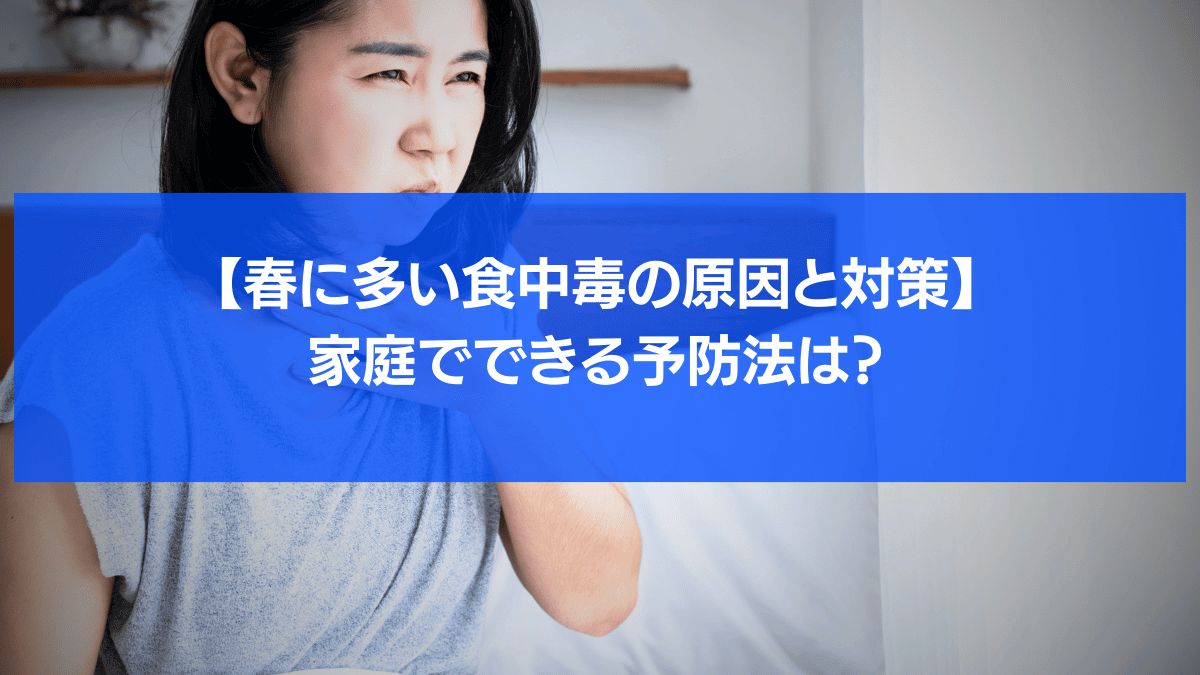
春は気温の上昇とともに、細菌やウイルスの活動が活発化し始める季節です。
冬の間はあまり気にしていなかった「食中毒」も、春になると一気にリスクが高まります。
春に発生しやすい食中毒の種類や原因、家庭でできる予防対策について解説していきます。
あわせて読みたい


【感染性胃腸炎とは】種類や感染経路、症状や予防策は?
冬の時期は、乾燥して風邪をひきやすくなるだけでなく、感染性胃腸炎にかかる人も多くなってくるので気をつけたいですね。感染性胃腸炎とは、病原大腸菌・細菌・ウイル…
目次
春に食中毒が増える理由
春は、日中の気温が20度近くまで上がる日も多くなり、細菌の繁殖に適した環境が整い始めます。
さらに、新生活による生活リズムの変化や、お弁当を作る機会が増えることも、食中毒のリスクを高める要因とります。
春に多い食中毒の原因菌・ウイルス
1. 黄色ブドウ球菌
- 【特徴】手指に存在する常在菌。お弁当やおにぎりの調理時に混入しやすい。
- 【症状】吐き気、嘔吐、下痢などが数時間で発症。
- 【予防法】手洗いを徹底する、素手で食品を扱わない(使い捨て手袋やラップを使用)。
2. サルモネラ菌
- 【特徴】加熱不十分な卵や鶏肉に多く存在。
- 【症状】腹痛、下痢、発熱。
- 【予防法】鶏肉や卵はしっかり加熱する。調理器具の洗浄を徹底。
3. カンピロバクター
- 【特徴】鶏肉に多い。少量でも感染する。
- 【症状】発熱、腹痛、水様便など。
- 【予防法】生肉と他の食品の接触を避ける。中心温度75℃以上でしっかり加熱。
特に注意!春のお弁当による食中毒
春は行楽シーズンや新学期の始まりで、お弁当を持って出かける機会が増えます。
しかし、お弁当は調理から食べるまでに時間が空くため、食中毒のリスクが高まるのです。
お弁当作りの注意点
- 十分に加熱したおかずを使う
- 汁気の多いものは避ける
- ごはんやおかずはしっかり冷ましてから詰める
- 保冷剤や保冷バッグを活用する
- 前日の残り物は極力避ける
春の食中毒を防ぐための5つのポイント
- 手洗いの徹底
調理前・トイレの後・外出から戻った後など、こまめな手洗いを。 - 清潔な調理環境を保つ
まな板、包丁、ふきんなどは定期的に洗浄・消毒。 - 食材は新鮮なものを選ぶ
賞味期限だけでなく、保存状態や臭いにも注意。 - 温度管理を徹底する
冷蔵・冷凍の食材はすぐに冷蔵庫へ。お弁当には保冷グッズを活用。 - 調理後は早めに食べる
長時間の放置は細菌の繁殖を招きます。
あわせて読みたい


【手洗い・うがい】感染症予防においての重要性と正しいやり方は?
近年わたしたちを悩ませ続けている新型コロナウイルス感染症をはじめ、わたしたちは常日頃から様々な感染症にかかるリスクにさらされています。感染症の予防を呼びかけ…
まとめ
春は気温の上昇とともに、細菌やウイルスの活動が活発化し始める季節です。
油断していると食中毒にかかるリスクが高いので注意しましょう。
日々のちょっとした意識と行動で、家族や自分の健康を守ることができます。
特に気温が上がり始める3月〜5月は要注意です。
お弁当や家庭での食事の管理を見直して、安心して訪れる春を楽しめるようにしていきましょう。
あわせて読みたい

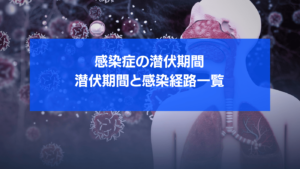
感染症の潜伏期間を教えて!潜伏期間や感染経路を一覧で解説
感染症には潜伏期間があり、感染症によって潜伏期間が異なります。家族や身近な人が感染症にかかった際はその感染症の潜伏期間を把握しておくことで二次感染、三次感染…